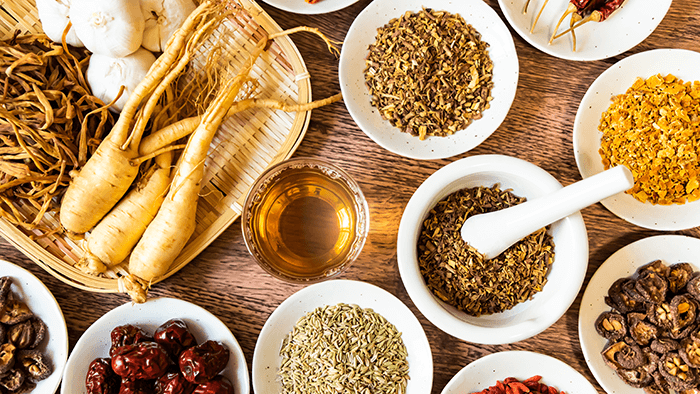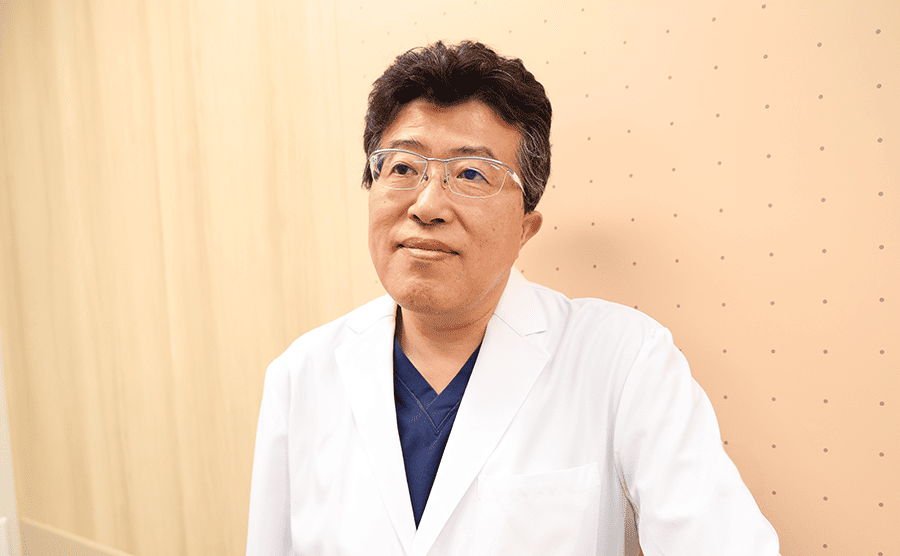「便秘が続いたと思えば、急に下痢になる」
そんな予測不能なお腹のトラブルを放置していませんか?
繰り返す不調は腸がSOSを出している大切なサインかもしれません。偽性下痢や過敏性腸症候群、大腸ポリープなど、放置すれば深刻な病気につながる可能性もあります。
この記事では、便秘から急に下痢になる原因と考えられる病気をわかりやすく解説します。症状との向き合い方やセルフケアのポイントもご紹介します。
ご自身の症状の裏に何が隠れているのかを正しく理解し、つらい毎日から抜け出すための第一歩を踏み出しましょう。
便秘と下痢を繰り返す主な原因
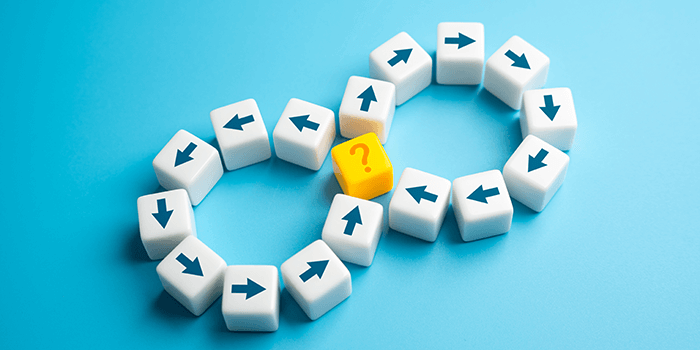
不安定な便通は、複数の要因が複雑に絡み合い、腸の機能が乱れることで生じています。便秘と下痢を繰り返す主な原因は以下の3つです。
- 偽性下痢(溢流性下痢)
- 自律神経の乱れ
- 腸内細菌の乱れ
偽性下痢(溢流性下痢)
偽性下痢(ぎせいげり)、または溢流性下痢(いつりゅうせいげり)とは、下痢ではなく便秘が原因で起こる症状です。見かけ上は下痢のように思えても、根本には直腸に硬い便が溜まり栓のようになっている状態です。
そのため、水分の多い便だけが隙間から漏れ出し、泥状の便が続きます。特に高齢者や寝たきりの方に多く見られるのが特徴です。誤って下痢止めを服用すると腸の動きがさらに弱まり、便秘が悪化する危険があります。
偽性下痢を疑う目安として次のようなサインが挙げられます。
- 水のような便が出ても固形物が混ざらない
- 強い便意がないのに下着が汚れることがある
- お腹が張って苦しいのに下痢便が出る
- 便秘薬を飲んでも下痢便しか出ない
これらの症状があるときは自己判断で下痢止めを使わず、医療機関で適切な治療を受けることが改善への第一歩となります。
自律神経の乱れ
自律神経の乱れは、便秘や下痢を繰り返す大きな要因です。腸のぜん動運動は自律神経によって自動的に調整されており、交感神経と副交感神経がバランスを取りながら機能しています。
それぞれの特徴と腸への影響を整理すると次のようになります。
| 神経の種類 | 働き | 腸への影響 |
| 交感神経 | 緊張・興奮・ストレス (アクセル役) | ぜん動運動を抑制し便秘傾向になる |
| 副交感神経 | リラックス・休息・睡眠 (ブレーキ役) | ぜん動運動を促進し排便を促す |
現代社会では、過労や睡眠不足、人間関係の悩みなどのストレスが重なり、このバランスが簡単に崩れてしまいます。その結果、交感神経が優位になると便秘が続き、副交感神経が強く働くと下痢が起こります。
両者の切り替わりが不安定になると、便秘と下痢を交互に繰り返す状態へとつながっていきます。
腸内細菌の乱れ
腸内細菌の乱れも、便秘や下痢を引き起こす要因の一つです。私たちの腸内には100兆個以上の細菌が存在し、善玉菌・悪玉菌・日和見菌がバランスを取り合うことで「腸内フローラ」と呼ばれる生態系を築いています。
健康な状態ではバランスが保たれていますが、便秘が続くと便が長く腸内に滞り、悪玉菌が増殖しやすくなります。増えすぎた悪玉菌は腐敗ガスや有害物質を生み出し、腸の粘膜を刺激します。
その刺激が腸の防御反応を誘発し、水分の過剰分泌や異常な収縮を招き、突然の下痢につながるのです。腸内環境を整える手段として善玉菌を補う食品やサプリメントが注目されていますが、研究によると効果には大きな個人差があります。(※1)
便秘と下痢を繰り返す症状で疑われる病気

便秘と下痢を交互に繰り返すとき、その背景にある病気は多岐にわたります。日常生活の支障につながるものや、早期発見が重要な病気も含まれています。
代表的な疾患としては次のようなものが挙げられます。
- 過敏性腸症候群(IBS)混合型
- 炎症性腸疾患(IBD)|クローン病・潰瘍性大腸炎
- 大腸ポリープ・がんなどの腸の病気
過敏性腸症候群(IBS)混合型
過敏性腸症候群(IBS)は、大腸内視鏡検査やその他の検査で異常が見つからないにもかかわらず、腹痛や便通異常が続く機能性の病気です。便秘と下痢を交互に繰り返す混合型(IBS-M)は、症状の不安定さが特徴です。
原因はストレスや不安、生活リズムの乱れが自律神経に影響し、腸が過敏に反応することや、ぜん動運動の異常が関与すると考えられています。代表的な症状は次のとおりです。
- 排便後に一時的に腹痛が楽になる
- 便秘と下痢を繰り返す
- お腹の張りや膨満感がある
- ガスが溜まりやすくおならが増える
- 排便後にも便が残っている感じがする
特に若い世代や働き盛りの人に多く、会議や通勤電車などの緊張する場面で悪化しやすいことも特徴です。命に関わる病気ではありませんが、生活の質を大きく低下させるため、専門医に相談して正しい診断と治療を受けることが重要です。
炎症性腸疾患(IBD)|クローン病・潰瘍性大腸炎
炎症性腸疾患(IBD)は、腸に原因不明の慢性炎症が生じる器質的な病気の総称で、潰瘍性大腸炎とクローン病の2つに大別されます。いずれも国の指定難病ですが、適切な治療により症状のコントロールは可能です。
以下の表で、両者の特徴をまとめています。
| 項目 | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 |
| 主な炎症場所 | 大腸の粘膜 | 口から肛門までの消化管全体 |
| 炎症の深さ | 粘膜の浅い層 | 腸壁の深い層に及ぶことがある |
| 主な症状 | 粘血便(粘液と血液が混じった便)、 下痢、腹痛 | 腹痛、下痢、体重減少、発熱、肛門病変 |
一見するとIBSに似ていますが、腸組織そのものに炎症が起きるため、血便や原因不明の体重減少、発熱などを伴いやすい点が大きな違いです。クローン病は、炎症による腸の狭窄から便秘が起こることもあります。
こうした症状がみられる場合は自己判断で様子を見るのではなく、早めに消化器内科を受診することが重要です。
大腸ポリープ・がんなどの腸の病気
大腸ポリープや大腸がんなど、腸に腫瘍ができる器質的な病気が便秘と下痢を繰り返す原因になることがあります。腸の壁にできた腫瘍が大きくなると通過路が狭くなり、便秘と下痢が交互に起こります。
仕組みと注意すべきサインを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 内容 |
| 症状が起こる仕組み | 1.腫瘍で腸が狭窄する 2.便が通りにくく便秘になる 3.溜まった便の隙間を水分の多い便が通り抜け下痢のように出る |
| 特に症状が出やすい部位 | 下行結腸や直腸など肛門に近い部位 |
| 大腸がんを疑うサイン | 便秘と下痢の繰り返し、血便、便が細くなる、腹部の張りやしこり、残便感、体重減少 |
慢性的な便秘自体も体に大きな負担をかけ、排便時の強いいきみが骨盤臓器脱などのリスクを高める可能性が指摘されています。(※2)
上記のサインが1つでも当てはまる場合は、早めに消化器内科で大腸内視鏡検査などの精密検査を受けることをおすすめします。
便秘と下痢を繰り返すときに病院に行くべき症状

便秘や下痢の繰り返しが続くとき、体はすでに異常のサインを出していることがあります。次のような症状が現れている場合は、受診の目安として注意深く確認することが大切です。
- 貧血を指摘された
- 発熱が続いている
- 血便が出る
- 激しい腹痛がある
- 体重が急に減少した
①貧血を指摘された
健康診断や検査で「貧血ですね」と言われたことはありませんか。お腹の不調と貧血は関係ないと思われがちですが、実は腸の病気を見つける大切なサインになることがあります。
大腸がんやポリープ、炎症性腸疾患などがあると、腸の粘膜からごくわずかな出血が続くことがあります。この出血は「便潜血」と呼ばれますが、毎日のように少しずつ鉄分が失われていくことで貧血が進んでしまいます。
貧血が進行すると、次のような症状が現れやすくなります。
- 顔色が青白く見える
- 少し動いただけで動悸や息切れがする
- 疲れやすく、体がだるい
- 急に立ち上がったときに立ちくらみやめまいがする
これらの症状に心当たりがあり、さらに便秘や下痢といった便通の異常もある場合は、腸のどこかで出血が続いている可能性があります。放置せずに消化器内科を受診し、詳しい検査を受けることが安心につながります。
②発熱が続いている
便秘や下痢に加えて37.5℃以上の熱が何日も続いたり、ぶり返したりする場合は注意が必要です。数日の発熱であれば一時的な不調のこともありますが、長く続く熱は腸の中で炎症が起きているサインかもしれません。
感染性腸炎やクローン病、潰瘍性大腸炎、大腸憩室炎などが考えられます。市販の薬で一時的に熱を下げても、根本的な原因の解決は難しいです。
お腹の症状と発熱が同時に続くときは、自己判断せずに内科や消化器内科で早めに相談することが大切です。
③血便が出る
便に血が混じる「血便」は、消化管のどこかから出血していることを示す、重要なサインです。血便と一言でいっても、その色や状態によって、出血している場所をある程度推測できます。
血便の色の違いと、考えられる主な病気を以下の表にまとめています。
| 色・状態 | 見た目 | 考えられる出血の場所 | 主な病気 |
| 鮮血便 | 真っ赤な血液、便の表面に付着 | 肛門、直腸など出口に近い部分 | 痔、直腸がん、ポリープ |
| 暗赤色便 | いちごジャムのような赤黒い色 | 大腸の奥の方 (上行結腸など) | 大腸がん、炎症性腸疾患、憩室出血 |
| 黒色便 | イカ墨や海苔の佃煮のような黒い便 | 胃、十二指腸 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん |
| 粘血便 | 血液とネバネバした粘液が混じった便 | 大腸 | 潰瘍性大腸炎、感染性腸炎 |
便秘と下痢を繰り返す症状に血便が伴う場合は、大腸がんや炎症性腸疾患などの可能性も考えられます。「どうせ痔だろう」と自己判断せず、消化器内科を受診して原因を調べてもらうことが大切です。
④激しい腹痛がある
便秘や下痢に伴う腹痛は珍しくありませんが、冷や汗が出るほどの強い痛みは放置してはいけません。命に関わる病気が隠れている可能性があるため、以下の特徴があるときは迷わず医療機関を受診してください。
- 脂汗が出るほどの痛み
- 痛みで体を伸ばせない、動けない
- 時間とともに痛みがどんどん強くなる
- お腹が硬く張ってパンパンになっている
- 吐き気や嘔吐を何度も繰り返す
これらは一時的な不調ではなく、腸の重大なトラブルにつながる危険があります。市販の鎮痛薬でごまかさず、夜間や休日でも速やかに受診することが大切です。
⑤体重が急に減少した
特別なダイエットや運動をしていないのに体重が急に減る場合は、体の病気が隠れているサインです。 栄養の吸収がうまくいっていないか、体が栄養を大量に消耗している可能性があります。
目安として、半年間で体重が5%以上減少したときは、体に何らかの問題が隠れている可能性があります。例えば、体重60kgの人なら、3kg以上減った場合は一度原因を確認してみると安心です。
体重減少とともに便秘や下痢を繰り返す場合、以下のような消化器の病気が考えられます。
- 大腸がん
- 炎症性腸疾患(IBD)
- 吸収不良症候群
「食欲がない」「食べても太らない」「疲れやすい」などの症状を伴う体重減少は、体からの危険信号です。放置せず、早めに医師へ相談しましょう。
便秘と下痢を繰り返すときに自分でできる症状の改善法

便秘と下痢を繰り返すつらい症状は、日々の生活の質を大きく下げてしまいます。症状が比較的軽い場合は、ご自身の生活習慣を見直すことが改善への一歩です。今日から始められる具体的なセルフケアの方法は以下の6つです。
- 食物繊維をバランス良く摂る
- 消化に負担のかかる食品を避ける
- 下痢止めや便秘薬を使用する
- 運動で自律神経を整える
- 睡眠習慣を見直す
- ストレスをためない工夫をする
①食物繊維をバランス良く摂る
腸の調子を整える基本は食事であり、特に食物繊維は欠かせない栄養素です。 食物繊維には「水溶性」と「不溶性」の2種類があり、それぞれ異なる働きを持っています。この2つをバランス良く摂ることが、安定したお通じにつながります。
代表的な特徴と食品例を表にまとめました。
| 種類 | 働き | 食材の例 |
| 水溶性食物繊維 | 水に溶けてゲル状になり便を柔らかくする善玉菌のエサとなり腸内環境を整える | 海藻類(わかめ、昆布、もずく)、こんにゃく、バナナ、りんご、オクラ、里芋、大麦 |
| 不溶性食物繊維 | 便のかさを増やして腸を刺激し、ぜん動運動を促す | 玄米、大豆・小豆、きのこ類、ごぼう、たけのこ、さつまいも |
水溶性は便秘と下痢を繰り返す方にも適しています。不溶性は便秘改善に効果が期待できますが、摂りすぎるとお腹の張りにつながることもあります。
まずは海藻や果物など水溶性を多めに取り入れ、便の状態を見ながら玄米やきのこ類など不溶性を少しずつ摂取するのがおすすめです。
②消化に負担のかかる食品を避ける
便秘と下痢を繰り返す時の腸はデリケートで、わずかな刺激でも症状が悪化することがあります。そのため、消化に時間がかかったり、腸を刺激したりする食べ物は控えることが大切です。
揚げ物や脂身の多い肉、ラーメン、生クリームなど脂質を多く含む料理は、消化に時間がかかり、腸に大きな負担をかけます。唐辛子やこしょう、カレー粉などの香辛料も腸の粘膜を刺激し、下痢を招くことがあります。
冷たい飲み物や炭酸飲料は腸の動きを乱したり、お腹の張りを強めたりする原因になります。アルコールは腸を過剰に動かし、多量のカフェインも刺激になるため、注意が必要です。
人によっては「高FODMAP」と呼ばれる糖質を含む食品(小麦、乳製品、玉ねぎ、豆類など)がガスや腹痛を引き起こすこともあります。特定の食品で調子が悪いと感じる場合は一時的に控え、体調の変化を観察すると良いでしょう。
③下痢止めや便秘薬を使用する
市販薬を使って一時的に症状を和らげることもできますが、あくまで対症療法であり根本解決にはなりません。 自己判断で長期間使い続けると、逆効果になることもあるため注意が必要です。
代表的な薬の特徴を整理すると次のようになります。
| 薬の種類 | 特徴・メリット | 注意点 |
| 下痢止め薬 | 通勤や会議前など「どうしても下痢を止めたい時」に有効 | ・感染性胃腸炎では原因を体外に出せず回復が遅れる ・偽性下痢では便秘を悪化させ逆効果 |
| 便秘薬 | 排便を促し即効性がある | 刺激性タイプを常用すると腸が慣れてしまい薬なしで排便しにくくなる |
| 整腸剤 (プロバイオティクス) | 善玉菌を補い腸内環境を整える助けになる 穏やかに作用 | ・個人差が大きく誰にでも合うわけではない ・研究によっては効果に差が出ない報告もある(※1) |
どの薬を選ぶかは症状や体質によって異なります。迷った時や症状が続く時は、医師や薬剤師に相談することが大切です。
④運動で自律神経を整える
適度な運動は腸の働きを整え、便秘や下痢の改善に効果が期待できます。 特に、腸に直接働きかける効果と、自律神経を安定させる効果の2つが期待できます。
運動の主な作用は次のとおりです。
- 腸のぜん動運動を促す:歩行などでお腹の筋肉が動くと腸も刺激され、便を送り出す力が高まる
- 自律神経のバランスを整える:軽い運動は副交感神経を優位にし、ストレスで乱れがちな腸の動きを安定させる
おすすめはウォーキングや軽いジョギング、ヨガ、ストレッチなどの有酸素運動です。毎日30分程度、少し汗ばむくらいの強度で無理なく続けることが目標になります。
健康的な排便習慣を守るためにも、運動は欠かせない習慣です。
⑤睡眠習慣を見直す
腸の健康を整えるには、質の良い睡眠が欠かせません。 脳と腸は自律神経を通じてつながっており、この関係は「腸脳相関」と呼ばれます。
睡眠不足で脳が疲れると自律神経が乱れ、腸の働きも不安定になります。そのため、生活習慣を整えて十分な睡眠をとることが重要です。
質の良い睡眠をとるための工夫は次のとおりです。
- 就寝・起床時間を一定にする:休日も含めて同じリズムで体内時計を安定させる
- 寝る前のスマホやPCを控える:ブルーライトがメラトニンの分泌を妨げ入眠を遅らせる
- ぬるめのお風呂に浸かる:38〜40℃のお湯に就寝1〜2時間前に入ると眠りにつきやすい
- 夕方以降のカフェインやアルコールを避ける:覚醒作用や浅い眠りの原因になる
まずは毎日7時間程度の睡眠を確保することを目標に、できることから取り入れてみましょう。
⑥ストレスをためない工夫をする
腸は「第二の脳」と呼ばれるほどストレスに敏感な臓器です。緊張するとお腹が痛くなったり下痢をしたりするのは、自律神経が乱れて腸が異常に収縮するためです。
便秘と下痢を繰り返す症状の背景には、精神的な負担が関わることも多く、日常生活の中でストレスを解消することが改善につながります。ストレス解消法は人によって異なりますが、深呼吸や瞑想、音楽やアロマ、軽い運動や趣味の時間を持つことが役立ちます。
家族や友人に話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなり、腸の不調を和らげる助けとなります。ストレスを完全になくすことは難しいですが、こまめに発散する習慣を持つことで腸の働きは安定しやすくなります。
自分に合った方法を見つけ、ため込まない生活を心がけましょう。
まとめ
不安定なお腹の不調は、食事や運動、ストレスケアなどの生活習慣の見直しで改善が期待できます。まずは、ご自身でできることから試してみてください。
血便や急な体重減少、激しい腹痛などが見られる場合や、セルフケアを続けても症状が改善しない場合は、自己判断で放置してはいけません。その不調は、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患、大腸がんなどの病気が隠れているサインの可能性もあります。
つらい症状を「いつものこと」と諦めずに、ご自身の体の声に耳を傾け、不安なときは消化器内科などの専門医に相談しましょう。
内視鏡ベルラクリニック銀座では、便秘など消化器症状に関する相談も受け付けています。便秘で不安を感じている方は、お気軽にご相談ください。
参考文献
- Fátima Faní Fitz, Maria Augusta Tezelli Bortolini, Gláucia Miranda Varella Pereira, Gisela Rosa Franco Salerno, Rodrigo Aquino Castro. PEOPLE: Lifestyle and comorbidities as risk factors for pelvic organ prolapse-a systematic review and meta-analysis PEOPLE: PElvic Organ Prolapse Lifestyle comorbiditiEs. Int Urogynecol J, 2023, 34(9), p.2007-2032.
- Ponlakit Lojanatorn, Jirachart Phrommas, Pornthep Tanpowpong, Songpon Getsuwan, Chatmanee Lertudomphonwanit, Suporn Treepongkaruna. Efficacy of Bacillus clausii in Pediatric Functional Constipation: A Pilot of a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Indian Pediatr, 2023, 60(6), p.453-458.