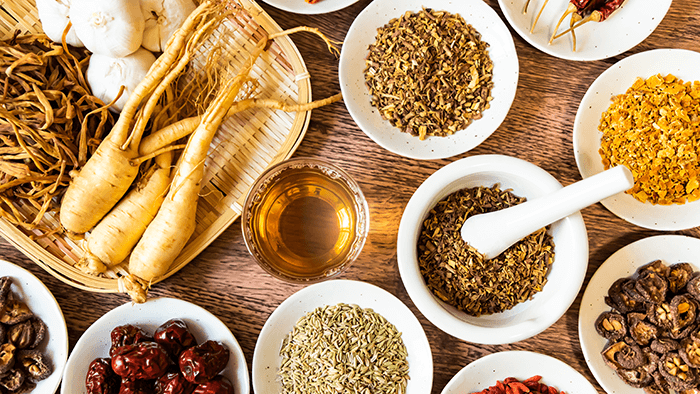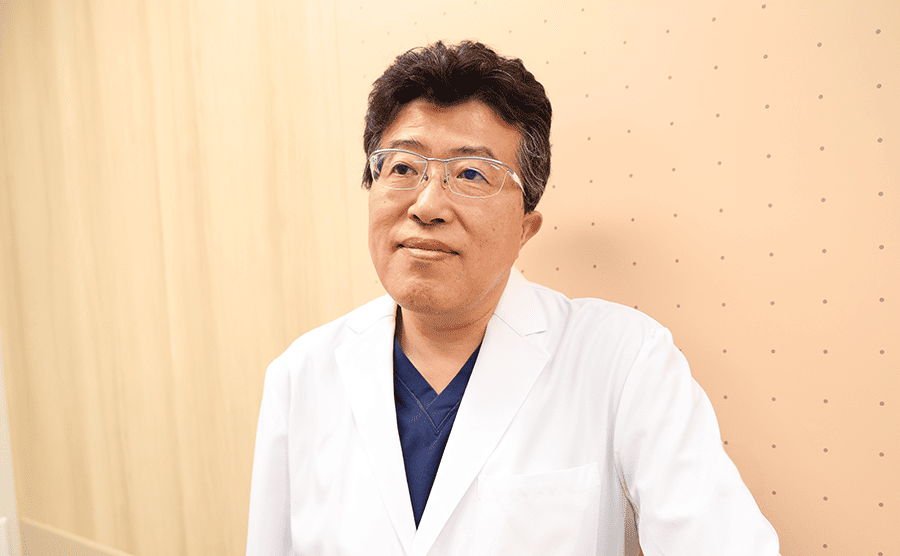お腹の張りやキリキリとした痛みを「便秘だから仕方ない」と放置していませんか?
多くの人が経験する便秘に伴う腹痛ですが、原因は便の滞留だけではありません。腸内で発生したガスの圧迫やストレスによる腸の収縮、腸内細菌の乱れなど、体からのサインはさまざまです。
病院での検査や治療が必要な病気が隠れていることもあります。この記事では、便秘で腹痛が起こる原因と、自宅でできる対処法、受診の目安や病院での検査の流れをわかりやすく解説します。
正しい知識を持つことで不安を軽くし、つらい症状を改善して、すっきりとした毎日を取り戻すヒントにつながるでしょう。
便秘で腹痛が起こる原因

便秘による腹痛は、単に便が溜まっていることだけが原因ではありません。便秘で腹痛が起こる代表的な原因として、以下の3つを解説します。
- ガスや便の滞留による圧迫・張り
- 腸が過剰に収縮する痙攣性便秘
- 腸内細菌のバランスの乱れ
①ガスや便の滞留による圧迫・張り
便秘による腹痛の多くは、腸に溜まった便やガスが腸を内側から圧迫することが原因です。
本来、腸のぜん動運動によって便はスムーズに運ばれますが、便秘になると流れが滞り、腸内に長く留まります。その間に細菌の働きでガスが発生し、腸が風船のように膨らむことで神経が刺激され、張りや痛みを感じるのです。
体質的に腸が長い「冗長結腸」は、便やガスがさらに溜まりやすく腹痛につながることがあります。これは病気ではなく解剖学的な特徴で、検査で偶然見つかることも少なくありません。
冗長結腸の特徴には次のようなものがあります。
- S状結腸が長い:骨盤よりも上の位置まで伸びている
- 横行結腸が垂れ下がっている:骨盤の位置まで垂れ下がっている
- 結腸に余分なループ(曲がり)がある:肝臓や脾臓の近くで、腸が複雑に曲がりくねっている
このように腸の形そのものが、便秘に伴う張りや腹痛を起こしやすい背景になっているケースもあります。
②腸が過剰に収縮する痙攣性便秘
便秘の中には腸の動きが弱まるのではなく、逆に動きすぎて痛みを起こす「痙攣性便秘」があります。自律神経の乱れによって腸が部分的に痙攣し、便の通り道が狭くなると、下腹部に差し込むような痛みが生じます。
原因にはストレスや過労、生活リズムの乱れがあり、若い世代や過敏性腸症候群(IBS)の便秘型でもよく見られます。セルフチェックの目安は以下のとおりです。
【痙攣性便秘のセルフチェック】
- ストレスを感じるとお腹が痛くなる
- 下腹部に痛みが起こりやすい
- コロコロした硬い便が出る
- 便秘と下痢を繰り返すことがある
- 排便後に痛みが和らぐ
- 食後に痛みが強くなる
痙攣性便秘では、刺激性の便秘薬がかえって症状を悪化させることがあるため、自己判断での使用は避けましょう。
③腸内細菌のバランスの乱れ
便秘による腹痛には、腸内細菌のバランスの乱れが関わっていることがあります。腸には約100兆個もの細菌が存在し、善玉菌・悪玉菌・日和見菌が共存して「腸内フローラ」を作っています。
通常はバランスが保たれていますが、偏った食事やストレス、加齢、抗生物質の使用などで悪玉菌が優勢になると腸内環境が悪化します。悪玉菌が増えると食べ物の残りかすを腐敗させ、アンモニアや硫化水素などの有害物質やガスを発生させます。
これが腸を膨らませて張りを感じさせるだけでなく、粘膜を刺激して腸を敏感にし、ぜん動運動を乱す原因となります。腸内環境が乱れると便秘が悪化し、痛みも強まる悪循環につながるため、改善には腸内環境を整えることが大切です。
自宅でできる対処法

便秘による腹痛はつらいですが、食事や運動、生活習慣を少し整えるだけで和らぐことがあります。自宅でも実践できる方法として、以下の4つを解説します。
- 食物繊維と水分の適切な摂取
- 消化に負担をかけにくい食事の工夫
- 運動やストレッチによる腸の刺激
- 良質な睡眠を確保する習慣
食物繊維と水分の適切な摂取
便秘を改善する基本は、食物繊維と水分をしっかり摂ることです。食物繊維には大きく2種類があり、それぞれ含まれる食品と働きを、以下の表にまとめています。
| 種類 | 主な食品例 | 働き |
| 水溶性食物繊維 | 海藻類、こんにゃく、バナナ、りんご、オクラ、オートミール | ・水に溶けてゲル状になり便を柔らかくする ・善玉菌のエサにもなり腸内環境を整える |
| 不溶性食物繊維 | きのこ類、豆類、ごぼう、玄米、さつまいも | 水分を吸収して便のかさを増やし、腸を刺激してぜん動運動を活発にする |
ただし、注意点もあります。腸が過敏になっている痙攣性便秘では、不溶性食物繊維の摂りすぎは腹痛や張りを悪化させることがあります。腹痛があるときは水溶性を中心に取り入れ、症状が落ち着いてから不溶性を少しずつ増やすと安心です。
また、食物繊維は腸で水分を吸収するため、水分不足では逆に便が硬くなります。1日1.5〜2リットルを目安にこまめな水分補給が大切です。特に朝の一杯の水や白湯は、腸を目覚めさせる良い習慣になります。
消化に負担をかけにくい食事の工夫
腹痛を伴う便秘のときは、腸が炎症や過敏な状態になっている可能性があります。そのようなときに消化の悪い食品を摂ると、腸に余計な負担をかけて症状が長引くことがあります。腸を休ませる意識を持ち、消化しやすく栄養のある食事を心がけましょう。
避けたい食品とおすすめの食品を以下の表にまとめています。
| 食事の工夫 | 食品の例 |
| 避けたい食品 | 揚げ物、脂肪の多い肉、バターや生クリーム、香辛料を多用した料理(カレー、麻婆豆腐など)、炭酸飲料、アルコール、冷たい飲み物やアイス |
| おすすめ食品 | おかゆ、よく煮込んだうどん、野菜スープ、豆腐、鶏ささみ、白身魚など消化の良い料理 |
食べるときは一度にたくさん摂らず、少量をゆっくりよく噛んで食べることが消化を助けます。
運動やストレッチによる腸の刺激
軽い運動やストレッチは、腸のぜん動運動を助け、便通を整える効果があります。激しいトレーニングは必要なく、心地良く続けられる範囲で取り入れることが大切です。
以下に、便秘改善に役立つ具体的な方法をまとめます。
| 方法 | やり方 | 効果 |
| ウォーキング | 1日20〜30分を少し早足で、特に食後に行うと良い | 腸の動きを自然に促す |
| ヨガ・ストレッチ | 軽く体を伸ばし血行を促進する | 自律神経を整えリラックス効果もある |
| お腹のマッサージ | 仰向けでひざを立て、へその周りを時計回りに「の」の字を描くようにさする | 腸を直接刺激し、排便を助ける |
| ガス抜きのポーズ | 仰向けで両ひざを胸に引き寄せる | お腹のガスを抜き張りを和らげる |
| ツボ刺激 (足三里) | ひざのお皿の下外側から指4本分下を5秒押して離す | 自律神経を整え、痛みや便秘を緩和する |
気持ちよく続けられる範囲で、毎日の生活に取り入れてみましょう。
良質な睡眠を確保する習慣
便秘や腹痛を改善するには、良質な睡眠の確保も大切です。睡眠中は副交感神経が優位になり、腸のぜん動運動が活発になります。この時間に日中の食事が消化・吸収され、便が作られるのです。
睡眠不足や不規則な生活が続くと自律神経のバランスが乱れ、腸の働きが鈍くなり、便秘や腹痛の引き金となります。毎朝同じ時間に起きて光を浴びる、夕食は早めに済ませる、寝る前のスマホやカフェインを避けるなどを意識することで睡眠の質は高まります。
ぐっすり眠ることが、腸を内側から整える方法です。
便秘に伴う腹痛で病院を受診すべきサイン

便秘による腹痛の中には、重大な病気が隠れているケースもあります。「いつものこと」と放置せず、気になる症状があれば早めの受診が大切です。
病院に相談すべき危険なサインは以下のとおりです。
- 経験したことのない激しい痛み
- 吐き気・嘔吐・発熱を伴う場合
- 血便や黒っぽい便が出る場合
- お腹の極端な張り
- 急激な体重減少
経験したことのない激しい痛み
一度も経験したことのないような激しい腹痛は、体からの緊急のサインです。冷や汗が止まらない、体を丸めないと耐えられない、声も出せないなどは、お腹の中で重大なトラブルが起きている可能性があります。
次のような特徴がある痛みには注意が必要です。
- 突然始まるバットで殴られたような痛み
- 時間とともにどんどん強くなる痛み
- 痛みの場所が移動する(例:みぞおちから右下腹部へ)
このような激痛を起こす病気には、腸閉塞や腸穿孔(ちょうせんこう)、急性虫垂炎、腹部大動脈瘤破裂など命に関わるものが含まれます。腸が詰まって血流が途絶えたり、腸に穴が開いて腹膜炎を起こしたりする場合は、耐えがたい痛みが生じます。
「動けないほど痛い」「意識がもうろうとする」場合は、一刻を争う状況です。ためらわずに救急車を呼ぶことが大切です。
吐き気・嘔吐・発熱を伴う場合
腹痛に加えて吐き気や嘔吐、37.5度以上の発熱があるときは、便秘以外の病気が隠れている可能性が高いサインです。これらの症状は体内で炎症や感染が進んでいることを示しており、特に発熱を伴う場合は注意が必要です。
代表的な病気は以下のとおりです。
| 病名 | 特徴 |
| 腸閉塞 (イレウス) | ・腸が詰まり内容物が逆流する ・嘔吐が強く進行すると便のような臭いを伴う嘔吐が出る |
| 虫垂炎・憩室炎 | ・虫垂や大腸の憩室に炎症が起きる ・腹痛とともに発熱や吐き気が出る |
嘔吐が続くと水分と電解質が急速に失われ、高齢者や子どもでは脱水が進みやすく危険です。市販の痛み止めや解熱剤を自己判断で使うと、症状を隠して診断を遅らせる恐れがあります。
このような症状があるときは、早めに医療機関を受診することが何より大切です。
血便や黒っぽい便が出る場合
便に血が混じる、あるいは黒っぽく変化するのは、消化管のどこかで出血している明確なサインです。出血部位によって便の色は異なり、その違いは診断の重要な手がかりとなります。
鮮やかな赤い血が便や便器に付く場合は、肛門や直腸からの出血が多く、痔や直腸がんの可能性も考えられます。赤黒い血の塊が混じる便は、大腸の奥からの出血を示し、大腸がんや憩室出血、炎症性腸疾患などが疑われます。
真っ黒でドロっとしたタール便は胃や十二指腸で出血しているサインで、潰瘍や胃がんなど重い病気の可能性もあります。
「お尻が切れただけだろう」と自己判断せず、医師の診察を受けてください。普段と違う便が出た際は、可能であれば写真を撮っておくと診断がスムーズになります。
お腹の極端な張り
普段の便秘の時よりもお腹が極端に膨らむときは、危険なサインです。以下のような特徴がある場合は注意してください。
- 指で叩くと太鼓のようにポンポンと響く
- お腹が硬く押してもへこまない(板状硬)
- 排便だけでなくおならも出ない状態が続く
- 張りと痛みが強く眠れない
これらは腸閉塞(イレウス)を疑う症状で、腸が完全に詰まって便やガスの通り道がふさがれると、腸内にガスが充満して異常な張りを起こします。放置すれば血流障害から壊死や穿孔を起こし、緊急手術が必要になることもあります。
一方、過敏性腸症候群(IBS)でも腹部の張りや痛みが出ることはありますが、多くは排ガスや排便によって症状が軽快します。もし排ガスが全く出ず、張りが次第に悪化するようであれば、腸閉塞などの重い病気の可能性もあるため、早急な受診が必要です。
急激な体重減少
便秘や腹痛とともに意図しない体重減少があるときは、特に注意が必要です。目安としては、半年間で体重の5%以上減った場合です。例えば体重60kgの方なら3kg以上の減少が該当します。
体重減少を伴う場合に考えられる主な病気には次のようなものがあります。
- 大腸がんなどの悪性腫瘍
- 炎症性腸疾患(クローン病・潰瘍性大腸炎)
- 甲状腺機能亢進症などの代謝異常
「夏バテかな」と自己判断せず、体重を数値で記録し、便秘とともに原因不明の体重減少がある場合は、消化器内科で精密検査を受けることが大切です。
病院での検査の流れ

便秘や腹痛が続くときは、専門の医療機関で原因を調べることが大切です。受診の流れを知っておくと、不安が減って安心して診察を受けられます。
病院で検査や診断がどのように進むのかを順を追って紹介します。
- 消化器内科や胃腸科を受診する
- 痛みの部位や頻度を具体的に伝える
- 検査する(腹部X線・内視鏡・血液検査など)
- 治療方針を決める
①消化器内科や胃腸科を受診する
便秘や腹痛を専門的に診てくれるのは、消化器内科や胃腸科です。これらの診療科は、食道・胃・小腸・大腸などの消化管や、肝臓・胆のう・膵臓などの臓器を幅広く扱っています。
かかりつけの内科がある場合は、まず相談し、必要に応じて専門科への紹介を受けるのも良い方法です。受診の際には、健康保険証やお薬手帳、紹介状や過去の検査結果、症状をまとめたメモを持参すると診察がスムーズです。
「これくらいの症状で受診して良いのだろうか」とためらう必要はありません。体の変化をきちんと伝えることが、原因を明らかにし、適切な治療につながる第一歩になります。。
②痛みの部位や頻度を具体的に伝える
診断を正確に進めるためには、症状をできるだけ具体的に伝えることが重要です。医師は患者さんの言葉を手がかりに病気の可能性を絞り込みます。そのため、診察前に以下の内容を整理しておくと、短い診察時間でも必要な情報を過不足なく共有できます。
- いつから症状が出たか
- 痛む場所はどこか
- 痛みの種類はどうか(例:キリキリ・シクシク・張り)
- 痛みの強さはどの程度か
- 痛みが強くなるタイミング(食後・空腹時・動作時)
- 便の状態(硬さ・形・色・血の有無)
- 排便で痛みが変化するか
- 併発症状があるか(吐き気・嘔吐・発熱・体重減少など)
特に便の色や形は診断の鍵になります。血便や黒色便が出た場合は、スマートフォンで写真を残しておくと、診察時により正確に伝えることができます。
③検査する(腹部X線・内視鏡・血液検査など)
正確な診断には、問診や診察だけでなく必要に応じた検査が欠かせません。症状や疑われる病気によって選択される検査は異なりますが、代表的なものは以下のとおりです。
| 検査名 | 主な目的・内容 |
| 血液検査 | ・炎症の有無(CRP・白血球数)や貧血(ヘモグロビン値)を確認 ・消化管からの出血が隠れていないかも評価 |
| 腹部X線 (レントゲン) | 腸内の便やガスの状態を確認し、腸閉塞の有無を調べる基本的な検査 |
| 腹部CT | ・炎症や腫瘍の有無を詳しく観察する ・腸の形態異常も評価できる |
| 大腸内視鏡検査 | ・肛門から細いカメラを入れて大腸粘膜を直接観察し、がんやポリープ、炎症を発見する ・必要に応じて組織を採取する |
すべての検査を一度に行うわけではなく、症状に合わせて医師が最適な検査を選びます。事前に説明を受けたうえで進めるため、安心して臨むことができます。
④治療方針を決める
検査結果をもとに、原因や生活背景に合わせて最適な治療方針を決定します。便秘や腹痛が続くときの治療は、症状の程度やライフスタイルに応じて、以下のような方法から選ばれます。
| 治療法 | 内容 |
| 生活習慣の指導 | 食物繊維・水分摂取の見直し、適度な運動、規則正しい排便習慣の指導 |
| 薬物療法 | 酸化マグネシウムなどで便を柔らかくする薬、腸の動きを助ける薬、整腸剤、腹痛緩和薬など |
| 内視鏡治療 | 大腸ポリープの切除や狭窄部の拡張など、便秘や腹痛の原因に直接アプローチする処置を行うことがある |
| 心理的アプローチ | 過敏性腸症候群(IBS)では、自律神経を整える薬や心理的サポートを組み合わせることもある |
治療は医師と患者さんが相談しながら二人三脚で進めるものです。不安や疑問があれば遠慮せず質問し、納得したうえで治療を始めることが改善への近道となります。
まとめ
便秘による腹痛は多くの人に起こる身近な症状ですが、日常生活を大きく妨げることもあります。まずは食事・運動・睡眠などの生活習慣を見直し、自宅でできるセルフケアを取り入れてみましょう。
経験したことのない激しい痛みや血便、極端な張りなど、この記事で紹介した危険なサインがある場合は要注意です。自己判断せず、速やかに医療機関を受診することが大切です。
「いつもと違う」と感じたら、ためらわずに消化器内科などの専門医に相談してください。正しい知識と適切な対応で、つらい痛みを和らげ、安心して過ごせる毎日を取り戻すことができます。
内視鏡ベルラクリニック銀座では、便秘など消化器症状に関する相談も受け付けています。便秘で不安を感じている方は、お気軽にご相談ください。