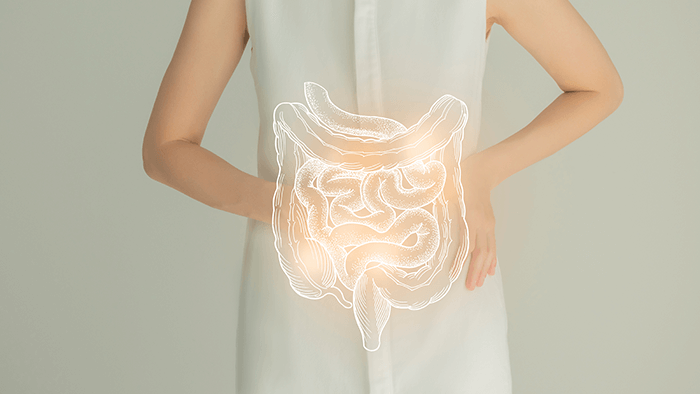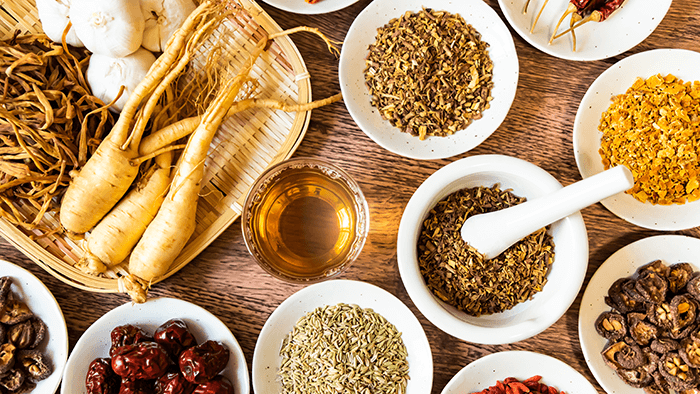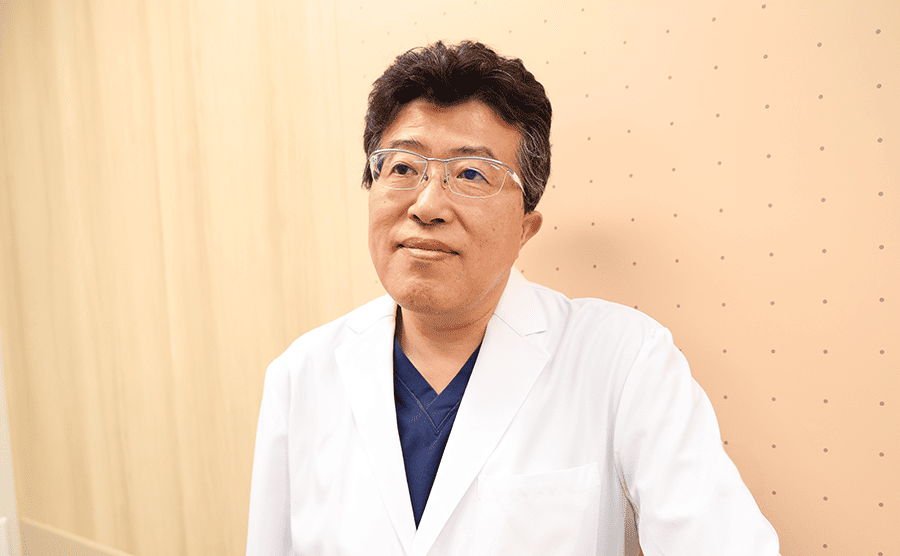便秘でお腹の張りや不快感に悩みつつも、「いつものこと」と軽視していませんか。便秘には、単なる不調では済まされない重大な病気が隠れている可能性があります。安易な自己判断は、体からの危険なサインを見逃しかねません。
この記事では、便秘の種類ごとの原因と特徴、見逃してはいけない危険なサインを詳しく解説します。自身の状態を正しく理解し、つらい症状を根本から改善する第一歩にしてください。
便秘とは?

便秘は、十分な量の便を快適に排出できない状態です。毎日排便があっても、量が少なかったりスッキリしなかったりすれば、便秘の可能性があります。
自身の状態を確認するために、以下の項目をチェックしてみましょう。
- 排便の回数が週に3回未満である
- 排便の際に強くいきむ必要がある
- 便が硬くて出しにくい
- 排便後も便が残っている感じがする
- お腹が張って苦しい
2022年の国民生活基礎調査によると、男性の27.5%、女性の43.7%が便秘を抱えています。(※1)便秘は、お腹の不快感だけでなく、肌荒れや食欲不振、イライラなど全身の不調につながりかねません。つらい症状は我慢せず、自身の状態を正しく知ることが大切です。
便秘の種類別|特徴と原因
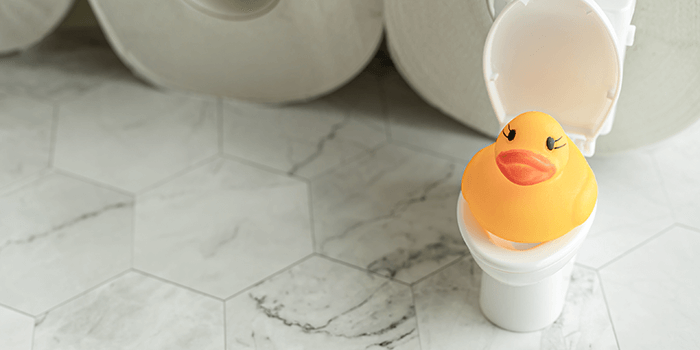
便秘の原因は、大きく以下の6つのタイプに分けられます。
| 大分類 | 小分類 | 詳細 |
| 機能性便秘 | 弛緩性便秘 | 大腸の筋肉が緩んでしまい、便を前に押し出すぜん動運動が弱くなる |
| 痙攣性便秘 | ストレスなどが原因で自律神経のバランスが乱れ、大腸が過度に緊張して痙攣する | |
| 直腸性便秘 | 便が肛門のすぐ手前にある直腸まで運ばれているにも関わらず、便意が起こりにくくなる状態 | |
| 器質性便秘 | 大腸がんなどの腸そのものに病気が隠れている状態 | 大腸がんなどの腸そのものに病気が隠れている状態 |
| 薬剤性便秘 | 服用しているお薬の副作用が原因で便秘が生じている状態 | 服用しているお薬の副作用が原因で便秘が生じている状態 |
| 症候性便秘 | ほかの病気が原因となって生じる |
- 弛緩性(しかんせい)便秘
- 痙攣性便秘
- 直腸性便秘
- 器質性便秘
- 薬剤性便秘
- 症候性便秘
①弛緩性便秘
弛緩性便秘は、大腸の筋肉が緩んでしまい、便を前に押し出すぜん動運動が弱くなることが原因で起こります。ぜん動運動が弱いと、便が大腸内にとどまる時間が長くなり、水分が過剰に吸収されるため、硬くて出しにくい便になります。
弛緩性便秘の主な症状は、以下のとおりです。
- お腹がパンパンに張って苦しい
- 排便後も、まだ便が残っている感じがする
- 食欲がわかない
- 肌荒れ・肩こり・イライラを感じやすい
弛緩性便秘は、水分や食物繊維の摂取不足や、極端なダイエットが大きな発症の原因です。まずは生活習慣全体を見直すことが、症状改善の鍵となります。
②痙攣性便秘
痙攣性便秘は、ストレスなどが原因で自律神経のバランスが乱れ、大腸が過度に緊張して痙攣することで起こります。腸が痙攣すると便の通り道が狭くなり、便がスムーズに運ばれないことが原因です。弛緩性便秘とは逆に、腸が必要以上に動きすぎている状態といえます。
痙攣性便秘は、腹痛や下痢を伴う過敏性腸症候群(IBS)の症状の一つとして現れることもあります。主な症状は、以下のとおりです。
- ウサギのフンのようなコロコロと硬い便が出る
- 便秘と下痢を交互に繰り返す
- 食後にお腹がキューッと差し込むように痛む
- お腹がゴロゴロと鳴ることが多い
精神的なストレスや環境の変化が、発症の大きな引き金となります。真面目で几帳面であったり、ストレスをため込みやすかったりする方がなりやすい傾向です。リラックスできる時間や十分な睡眠を取ることが、症状の緩和につながるでしょう。
③直腸性便秘
直腸性便秘は、便が肛門のすぐ手前にある直腸まで運ばれているにも関わらず、便意が起こりにくくなる状態です。直腸にあるセンサーが鈍くなることで、脳へ便を出す指令がうまく送れなくなり、出口で便の渋滞が起きているイメージです。
直腸性便秘の主な症状は、以下のとおりです。
- 便意をほとんど感じない、または弱い
- トイレで強く力をいれないと便が出ない
- 排便してもスッキリせずに残っている感じがする
- 栓になった硬い便の周りから液体状の便が漏れる
直腸性便秘の原因は、便意の我慢です。朝の忙しい時間帯や外出先でトイレを我慢する習慣が続くと、直腸の神経の感度が低下してしまいます。高齢による神経機能の低下や、痔の痛みで排便をためらってしまうことも原因となります。
まずは決まった時間にトイレに座る習慣をつけ、便意を逃さないことが大切です。
④器質性便秘
器質性便秘は、機能性便秘(弛緩性便秘・痙攣性便秘・直腸性便秘)とは根本的に原因が異なります。大腸がんや大きなポリープ、炎症性の病気(クローン病など)により、物理的に腸管内が狭くなることで起こる便秘です。腸の通り道が狭くなっているため、便が通過できなくなります。
主に以下の病気が原因となって器質性便秘は起こります。
- 大腸がんや大腸ポリープ
- クローン病や潰瘍性大腸炎
- 腸閉塞(イレウス)
- 腹部手術後の腸管の癒着
器質性便秘の方は、原因となっている病気の治療が最優先です。便秘に加えて、激しい腹痛や吐き気・嘔吐、血便、発熱がある場合は、自己判断で市販薬を使ってはいけません。
腸が塞がりかけている状態で下剤を服用すると、腸内の圧力が異常に高まり、命に関わる事態を招く危険性があります。
⑤薬剤性便秘
薬剤性便秘は、服用中の薬の副作用によって引き起こされるタイプです。薬の成分が腸のぜん動運動を抑制したり、便の水分を減らしたりすることで発症します。ただし、自身の判断で服用を中止すると、治療中の病気が悪化する可能性があるため注意してください。
便秘の原因となりやすい主な薬を、以下の表にまとめました。
| 薬 | 治療対象の病気 |
| 医療用麻薬(オピオイド鎮痛薬) | がんなど |
| 抗うつ薬、抗精神病薬 | うつ病、統合失調症など |
| 抗コリン薬 | 咳止め、頻尿、パーキンソン病など |
| 鉄剤 | 貧血 |
特に、がんの痛み治療で使われるオピオイド鎮痛薬による便秘は、強い不快感をともなうことが多く、専門的な対応が必要です。通常の便秘薬に加え、オピオイドの作用を腸でブロックする特殊な薬(PAMORAなど)を使って治療することがあります。(※2)
お薬を飲み始めてから便秘が気になるようになった場合は、処方した医師や薬剤師に相談してください。
⑥症候性便秘
症候性便秘とは、ほかの病気が原因となって生じる便秘のことを指します。
代表的なものとして、甲状腺機能低下症や糖尿病、高カルシウム血症などの内分泌・代謝の異常があり、腸の働きを鈍らせることで便秘を引き起こします。
また、パーキンソン病や脊髄損傷、多発性硬化症といった神経疾患でも、腸の運動や排便をコントロールする神経の働きが障害されるため、便秘が起こりやすくなります。
症候性便秘は生活習慣だけでは改善が難しく、背景にある病気を見極めて治療することが重要です。大腸内視鏡検査を行い、器質的な異常の有無を確認したうえで、必要に応じて内分泌疾患や神経疾患などの精査へと進みます。
便秘の予防法

便秘のなかでも機能性便秘であれば、生活習慣の改善で予防できる可能性があります。便秘の予防法は以下の3つです。
- 水分を積極的に摂取する
- 食生活を見直す
- 適度に運動する
水分を積極的に摂取する
便秘を予防するために基本的で重要なことは、十分な水分摂取です。
便の大半は水分で構成されています。体内の水分が不足すると、腸が便から水分を過剰に吸収してしまい、結果として便が硬く、排出しにくい状態になります。
便秘にならないよう、1日に1.5〜2リットルを目安に、こまめに水分を摂ることを心がけましょう。一度に大量に飲むと尿として排出されやすいため、コップ1杯程度(150〜200ml)を1日に何回も分けて飲むことを推奨します。
特に朝起きてすぐにコップ1杯の水を飲む習慣は、おすすめです。空っぽの胃に水分が入ると、大腸の動きが活発になり、自然な便意が促されます。冷たい水は胃腸に負担をかけることがあるため、常温の水や白湯を飲みましょう。
ただしカフェインやアルコールを含む飲料には利尿作用があります。摂取しすぎると水分不足になり便が硬くなることがあるので、注意してください。
食生活を見直す
毎日の食事は、腸の健康や便通の状態に影響します。便秘を予防するためには、食物繊維と発酵食品を意識した食事が鍵となります。
まず、1日3食をできるだけ決まった時間に摂り、腸に規則正しいリズムを作ってあげることが大切です。食事のリズムを整えたうえで、食物繊維を積極的に摂取しましょう。厚生労働省によると、30〜64歳であれば1日あたり男性で22g、女性で18gが食物繊維摂取量の目安です。(※3)
食物繊維だけでなく、腸内環境を整える善玉菌を増やすことも重要です。ヨーグルトや納豆、キムチなどの発酵食品を日常的に食べましょう。
適度に運動する
運動不足は、便秘を引き起こす大きな原因の一つです。体を動かさないと、血行が悪くなり、腸のぜん動運動が鈍くなるだけでなく、排便時にいきむために必要な腹筋の力も弱まってしまいます。
日常生活のなかに、無理なく続けられる運動を取り入れてみましょう。ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。全身の血行が良くなることで、腸の働きも自然と活発になります。
お腹周りの筋肉を直接刺激するエクササイズも便通改善が見込めます。腹筋運動やお腹のマッサージ、ストレッチ・ヨガなどを毎日少しずつでも継続することが大切です。
リラックスしながら体を動かす時間は、ストレスの解消にもつながります。
病院での検査が必要な便秘の症状

多くの便秘は、食事や運動など生活習慣の見直しで改善が期待できます。しかし、以下のような症状が見られる場合は、重大な病気が隠れているサインかもしれません。
- 激しい腹痛・嘔吐・血便・発熱が生じた
- 市販薬による改善が見られない
- 排便習慣が急に変化した
激しい腹痛・嘔吐・血便・発熱が生じた
便秘に加えて、以下のような症状が一つでも現れた場合、緊急性の高い病気が隠れている可能性があります。
- 我慢できないほどの激しい腹痛
- 繰り返す嘔吐
- 血便(便に血が混じる)
- 38度以上の発熱
上記は、器質性便秘で見られる症状です。腸がねじれたり塞がったりするイレウスや、大腸の壁にできたポケット状のくぼみに炎症が起きる大腸憩室炎などが原因で起こります。
お腹がパンパンに張って激痛が続く場合は、腸に穴が開く消化管穿孔を起こし、命に関わる腹膜炎に進展する危険があります。夜間や休日であっても、ためらわずに救急外来を受診してください。
市販薬による改善が見られない
ドラッグストアで手軽に購入できる便秘薬で1〜2週間ほど試しても症状が良くならない方は、専門的な診断が必要です。最初は効いていたのに、だんだんと薬の量を増やさないと効かなくなってきた場合も注意してください。
市販薬が効かない主な原因を、以下の表にまとめました。
| 考えられる原因 | 具体的な内容 |
| 薬と便秘タイプの不一致 | ストレスが原因の痙攣性便秘の方が、腸を無理に動かす刺激性下剤を使うと、けいれんが強まり腹痛が悪化することがある |
| 薬への依存 (耐性) | 同じ刺激性下剤を長期間使い続けると、腸が慣れてしまい、自力で排便する力が弱まってしまう |
| 隠れた病気の存在 | 大腸がんや炎症性の病気などが、便秘の原因として潜んでいる可能性がある |
自己判断で市販薬を使い続けることは、根本的な原因の発見を遅らせるリスクをともないます。「とりあえず薬を飲めば便が出るから」と安易に考えず、改善が見られない場合は消化器内科などを受診しましょう。
排便習慣が急に変化した
これまで快便だったのに急に便秘になったケースは注意が必要です。排便パターンが大きく変わった場合は、体の内部で何らかの変化が起きているサインかもしれません。
急激に起こる排便習慣の主な変化は以下のとおりです。
- ここ数か月で急に便秘がちになった
- 便秘と下痢を数日おきに繰り返すようになった
- 便が急に鉛筆のように細くなった
- 排便後も便が残っている感じが続く
- 理由なく体重が減ってきた
排便習慣の急な変化は、大腸がんや大きなポリープによって腸の内部が物理的に狭くなっている可能性があります。腫瘍が便の通り道を塞ぐことで、便が細くなったり、便秘と下痢を繰り返したりする原理です。
便秘は消化器の病気だけでなく、神経系の病気の初期症状として現れることもあります。例えば、パーキンソン病では、手足の震えといった運動症状が現れる何年も前から、頑固な便秘などの非運動症状がみられることが報告されています。(※4)
年齢に関わらず、自身の排便習慣に明らかな変化を感じた場合は、自己判断せず、専門の医療機関で検査を受けてください。
まとめ
便秘には、生活習慣の乱れやストレスが原因の種類がある一方、薬の副作用や病気などが起因するタイプもあります。機能性便秘であれば生活習慣の見直しで改善が期待できますが、大腸がんなどの重大な病気が隠れているおそれもあります。
「いつものことだから」と自己判断で市販薬を使い続けず、症状が長引いたり不安があったりする場合は、我慢しないでください。内視鏡ベルラクリニック銀座では、消化器疾患に関する相談を受け付けているため、お気軽にお問い合わせください。
参考文献
- 厚生労働省:「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」
- Mehta N, Laitman AP, Brookfield RB, Harris LA.Treatment of Opioid-Induced Constipation: Inducing Laxation and Understanding the Risk of Gastrointestinal Perforation.Journal of Clinical Gastroenterology,2025,59(6),491-496.
- 厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」.
- Yuan XY, Chen YS, Liu Z.Relationship among Parkinson’s disease, constipation, microbes, and microbiological therapy.World Journal of Gastroenterology,2024,30(3),225-237.